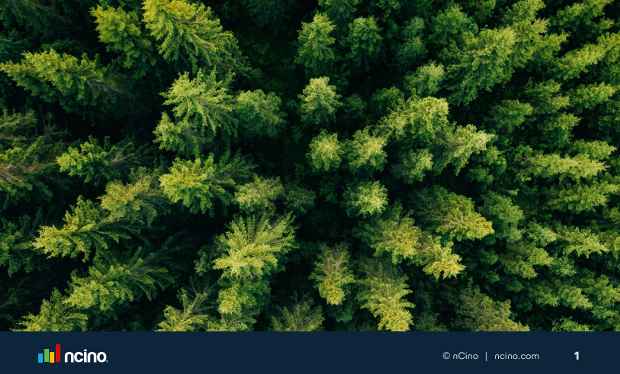代表の野村が、日本経済新聞社と金融庁が主催するイベント「FIN/SUM 2022」に登壇しました。3月29日から31日にかけての3日間にわたって行われたイベントの初日、野村は午前の単独講演と夕方のパネルディスカッションの2つに登壇し、デジタルで変革を成し遂げたいと考える日本の金融機関に向けて、nCinoという選択肢の存在を改めて訴えました。
■金融機関のシステム統合に向けて、nCino(エヌシーノ)からの提言

野村の講演は、「融資業務のDXと生産性向上実現に向けてーシステム統合の第一歩とは powered by nCino」と題したもので、最近の日本法人のビジネス概況とDXに取り組みたいと考えるお客様に向けての提案を主眼としたものです。米LiveOak銀行を前身とするnCinoは、銀行員が銀行員のために開発したソフトウェア製品で、お客様がデータ中心の銀行運営を実現できるよう、融資業務の効率化に役立つ機能を包括的に提供しています。既に米国で1,750以上の金融機関が利用中で、このビジネスを欧州、APAC、カナダへと拡大している最中です。
その中でも、日本は本社にとって重要な市場です。2019年末の日本法人設立以来、野村は人材採用、製品のローカライズ、認知の獲得、パートナーエコシステムの拡大など、nCinoを日本の金融機関のお客様に提供可能な状態にする活動に集中してきました。nCinoは気軽に使ってみようと思う種類の製品ではなく、お客様が採用を決定するには時間がかかります。一連の活動の成果が奏功し、2021年には3行との共同プロジェクトを開始できました。グローバルでは2022年に入ってからは、大手のお客様としてウェルズ・ファーゴが、中小企業向け融資業務にnCino採用を決定しました。
nCinoが特に拘っているのは、融資業務の効率化を通じてトップラインの向上を実現することです。そのためには裏側のシステムを変えなくてはなりません。しかし、これからDXに取り組もうとする日本の金融機関はシステム面でいくつかの課題を抱えています。特に深刻なのが「既存のプロセスやシステムの変更・修正が難しい」というものです。確かに、野村が日本法人代表に就任以来、多くのお客様から聞いた話を総合すると、高度に積み上げた基幹システムのロジックを一足飛びに変えるのは難しい。ですが、nCinoにデータを集約すれば、多重入力を減らすことは可能です。API連携でバックエンドの基幹系システムへ接続できるので、「最初はフロントのプロセスから変革を始め、未来への第1歩を踏み出してほしい」、そんな提案で野村は講演を締めくくりました。
■外資系企業本社の期待と日本市場の現実に横たわるギャップ

続いて夕方のパネルセッション「海外フィンテックの日本進出について、課題とその解決方法 powered by 金融庁」では、外資系企業がいかに日本市場の発展に貢献したいと考えているか。そして、日本の金融機関も外資系企業が提供するテクノロジーを必要としているかが明らかになりました。各自の自己紹介の後、金融庁の松澤翔太氏(総合政策局総合政策課フィンテック室 課長補佐)を聞き手に、シンガポールのスタートアップNIUMの越智一真氏と共に、野村は日本市場進出とビジネス拡大に向けてこれまで取り組んできたことを振り返りました。


2014年にシンガポールで会社設立したNIUMは、決済と送金のAPIを提供するサービスを提供する会社です。越智氏はこれまでのキャリアを通して、ゼロからの法人立ち上げの経験を積み重ねてきました。その経験から、「ゼロの状態からカントリーマネージャーとして入社する時、特に重要になるのが本国の創業者や他の幹部たちの期待と現実のギャップを埋めるコミュニケーション」と指摘しました。
通常、日本で金融業を行うにはライセンスの取得が不可欠です。本社は1年以内にサービス開始、2年程度での黒字化を期待するのですが、実際にはそれ以上の時間がかかることも少なくありません。法人設立から始まり、事業登録の申請、当局からの認可を経て、本格的にビジネスが立ち上がるまでに、どのぐらいの時間が必要かは市場環境でも変わってきます。一概にどの程度の時間が必要になるか、その目安があるわけではありませんが、初期段階から本社とのギャップを小さくしておくことが重要です。もっと言えば、言語やカルチャーの違いの考慮、さらには人材採用が思うように進まないリスクなどにも備える必要があります。
また、スタートアップのアーリーステージでは、1人で多くの役割をこなすことが求められる場面が多々あります。ストレスの多い環境に置かれることも多く、越智氏は思わぬことが起きても動じない胆力や変化への適応力が求められると語りました。
野村も越智氏の見解に同意を示します。nCinoはBtoBのビジネスで、金融機関のお客様に直接ソフトウェアを販売するビジネスモデルを採用しています。米国本社として契約したいお客様が1年で10行なのか、それとも3年で5行か。これだけでも日本法人のビジネス戦略は大きく変わります。前者であれば、ライセンスの再販ができるディストリビューターを増やす投資が必要です。逆に、直販だけと決めれば、どんな役割の人がいつまでに何人必要か、人材採用計画について本社から合意を得なくてはなりません。さらに、共同出資者であるJapan Cloudとも同じコミュニケーションが必要です。これらのステークホルダーとの合意があれば、日々のビジネス活動で迷いが生じることがあっても、基本に立ち戻ることが容易です。

■ペイパル、国境を越えたM&Aの狙い
また、ペイパルのピーター・ケネバン氏は、日本のスタートアップPaidyを買収統合した戦略的背景について、語りました。
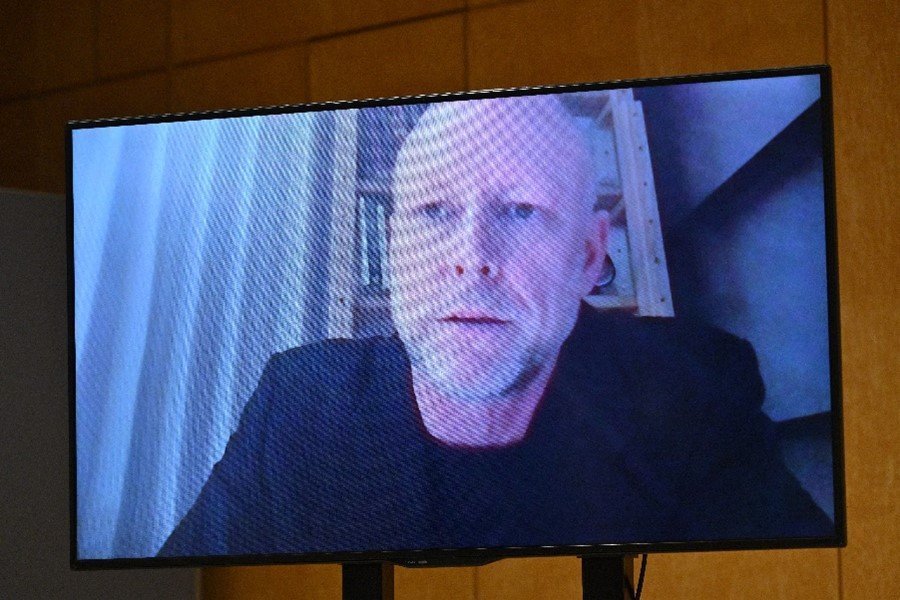
オンライン電子決済サービスのペイパルが、日本で本格的なビジネス展開を開始したのは2010年からです。同社の事業の柱は大きく2つ。1つが個人向けのPayPalウォレットの事業、もう1つがEC事業者向けの決済事業で、こちらはとりわけ越境ECに強みを持ちます。ケネバン氏が日本の事業責任者に就任したのは2021年4月。同年9月には後払い決済サービス「Paidy」の買収を発表するなど、M&Aも活用し、日本市場におけるプレゼンスをさらに高めていこうとしています。
その背景に何があったのか。ペイパルにとって、日本は何もしなくてもそれなりの成長は可能な市場です。しかし、高い成長目標を実現するにはどうするかと考えた時、現状維持の選択肢はない。同社が着目したのは越境ECでした。日本は国内市場の規模が大きいため、EC全体に占める越境の取引は10%未満ですが、海外ではこの比率がもっと高いのです。幸い、日本のEC事業者が販売している商品には魅力的なものが多く、事業者にとって、越境ECは自分たちのビジネスを伸ばすチャンスの眠る市場と言えます。これは事業者をサポートするペイパルにとっても、同様に成長機会をもたらすことを意味します。
ただし、チャンスを生かすには、言葉の壁、決済の壁、物流の壁など、様々なハードルを超えなくてはなりません。決済の壁を越えることはペイパルがサポートできても、他の壁はそうはいきません。「日本市場の特徴に合わせた戦い方をするにも、仲間を増やしたい」とケネバン氏は説明しました。そのための戦略が「合従連衡」です。協業の場合もあれば、買収の場合もある。越境ECにしても、国内ECにしても、ペイパルが今後の10年間に向けて飛躍的な成長を遂げるために仲間の力を借りる。それがケネバン氏の言う合従連衡の戦略の要点です。
Paidyは、元々ペイパルが社内に有するコーポレートベンチャーファンドPayPal Venturesが数年前から投資をしていたスタートアップで、ペイパルでも良い会社であることを理解していました。日本における成長戦略を見直していたのは、ケネバン氏が着任する前のことですが、戦略にフィットする企業としてPaidyがいた。この買収が戦略に即した意思決定だったと、ケネバン氏は解説しました。
■共同プロジェクトで得た数々の学び、島根銀行の場合
パネルには島根銀行の小川隆浩氏が参加し、他のパネリストとは異なる立場から示唆に富む見解を提示してくれました。

島根銀行にとっての転機は、2019年9月のSBI証券との資本提携にあります。この提携は業績改善をもたらしたと同時に、ビジネスを支えるシステム面でも多くの改善に取り組む機会を提供しました。今でこそ、多くの銀行がモバイルアプリを提供していますが、島根銀行ではコスト的に難しいとの判断から、やむを得ず導入を見送っていました。それが提携を機に一変。お客様とのデジタル接点になるWebサイトやアプリの強化が決定します。SBIからイスラエルのOpenLegacy社の紹介を得たのが2019年12月のことでした。
昨今のフロントエンドシステムの開発では、API連携が不可欠です。2週間程度の準備期間を経て、PoCのためにイスラエルからエンジニア5人ぐらいに島根まで来てもらったところ、本店が大騒ぎになったと、小川氏は当時を振り返ります。エンジニアの滞在予定は1週間程度でしたが、PoCは初日の午前中に成功するスピード感でした。実際のプロジェクト開始は2020年4月ですが、2021年6月に銀行アプリの参照系のリリース、2022年2月にMoney Tapとの接続、PayPayとの連携に成功し、現在進行中の更新系の開発が終われば、サービス開始という計画です。
プロジェクトは途中ですが、「イスラエルの会社と接点を持てたのはよかった」と小川氏は評価します。OpenLegacyとの関係をきっかけに、新しいことに取り組めるようになった行内のエンジニアたちは水を得た魚のように変わりました。高いモチベーションのおかげで、海外メンバーとの言葉の壁を感じることがあっても、全員がプロジェクトに集中していると小川氏は語ります。
一連の経験から、「島根銀行に限って言えば、海外にどんな優れた技術を持つ企業が存在するかがわかっていない。情報が少ないと実感しました。逆にやってみると、次々に新しい情報を得て、取捨選択できるようになっていくのかもしれません。今は、技術的に何が優れているかを判断できる人材の必要性を感じています」と小川氏は述べました。島根銀行の場合、行内にエンジニアがいることが強みでもあります。IT部門の機能をアウトソーシングした銀行と異なり、これまで組織に蓄積してきた技術ノウハウが活かせるからです。
新しい企業との仕事は、助っ人エンジニアを外から連れてくるのとは異なる種類の効果を組織にもたらします。その意味で、組織の中で目利き力を持つ人材を育てることが、今後の銀行業務の変革で必要になるでしょう。